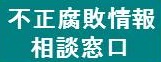 |
||
 |
||
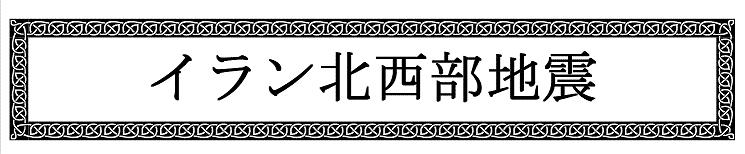 |
||
 |
||
 |
 |
 |
 |
日本の外交政策
〔2011年2月〕
【菅総理の「ダボス会議」出席――開国と絆(きずな)の必要性訴える】
1月26日から30日まで、スイスで開催された世界経済フォーラム(WEF)年次総会(通称「ダボス会議」)に出席した菅総理は、29日、「開国と絆」と題する特別講演を行った。この中で菅総理は、現在の日本で、精神面と経済面で閉塞を打ち破っていく「開国」が必要であると同時に、それにより人と人との関係に断絶が生じないよう、改めてつなぎ合わせる「絆」が必要であるとして、次のポイントに沿って、世界に向けてメッセージを発信した。
菅総理はまた、「日本の再構築」をテーマとして開かれたセッションの冒頭に出席し、日本及び日本人が自信を回復して外に出て行く必要性について述べた。同セッションでは、海江田経済産業大臣、緒方JICA理事長等がパネリストを務めた。
菅総理は訪問中、アナン前国連事務総長をはじめ、国際情勢に精通した有識者と密度の濃い意見交換も行った。有識者から、「人間の安全保障」に対する高い評価、「開国」における意識改革や人の移動の重要性、WTOドーハ・ラウンドや経済連携における日本のリーダーシップへの期待、日本の成長戦略(法人税減税を含む)への高い評価等への言及がなされた。
なお、スピーチの全文を含む、菅総理による本件会議出席の様子については、以下の首相官邸HP内も参照。
http://www.kantei.go.jp/foreign/kan/actions/201101/29davos_e.html
【北朝鮮人権状況決議の採択と強制失踪条約の発効――拉致問題解決に向けた日本の努力】
昨年12月21日、第65回国連総会本会議において、我が国及びEUが共同提出した北朝鮮人権状況決議が、6年連続で賛成多数により採択された。本決議では、北朝鮮における様々な人権侵害に強い懸念を表明し、北朝鮮に対し、すべての人権と基本的自由の尊重や、拉致被害者の即時帰国の実現を含めた拉致問題の早急な解決等を強く要求している。
北朝鮮の人権状況改善のためには、国際社会が連携して、北朝鮮に対して、改善に向けた具体的行動の働きかけを継続することが重要である。本決議が、すべての国連加盟国からなる国連総会本会議で、6年連続、多数の賛成票を得て採択されたことは、拉致問題の早期解決を含む北朝鮮の人権状況に対して引き続き強い懸念があることを示しており、北朝鮮に対し国際社会の明確なメッセージを改めて発出することになったと考える。
また、昨年12月23日、「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約」(強制失踪条約)が発効した。本条約は、拉致を含む強制失踪を犯罪として定め、その処罰の枠組みの確保及び予防に向け締約国がとるべき措置等について規定している。
本条約は、拉致を含む強制失踪が犯罪として処罰されるべきものであることを国際社会において確認するとともに、将来にわたって同様の犯罪が繰り返されることを抑止する意義がある。我が国としても、拉致を含む強制失踪への国際的な関心を高めるとの見地から本条約を重視しており、本条約の発効を歓迎している。
【第2回日本・アラブ経済フォーラム――エネルギー・環境、人材開発・教育・科学技術、投資、観光、金融、貿易等の分野での協力を推進】
昨年12月11日~12日、チュニジアのチュニスにおいて、日本及びアラブ連盟共催の下、第2回日本・アラブ経済フォーラムが開催され、我が国から前原誠司外務大臣、大畠章宏経済産業大臣が出席した。今般のフォーラムは、2009年12月に東京で開催された第1回に引き続き、日アラブ双方から総勢約1,100名が参加、うち閣僚級が、前原大臣及び大畠大臣を含め30名余り参加し、約40の協力プロジェクトが合意・発表されるなど、盛大にとり行われた。
開会式の挨拶の中で前原大臣は、魅力的な市場及び投資先へと変貌しつつあるアラブ諸国との間で、共に発展することを目指す対アラブ経済外交につき、インフラ整備への日本の先進技術活用の促進、年間4,000人のJICAによる研修員の受け入れ等による人材育成への貢献、GCC諸国とのFTA交渉の推進等を訴えた。大畠経済産業大臣からは、今次フォーラムを契機に、相互の信頼関係が一層深まることを祈念し、今次フォーラムが将来のビジネスの萌芽となることを期待する旨述べた。
日アラブ間の共同声明として今回発表された「チュニジア宣言」は、①エネルギー環境分野(特に太陽エネルギー、水、原子力)の協力、②人材育成、教育・科学技術分野(我が国の経済協力案件であるエジプト日本科学技術大学及びボルジェ・セドリア・テクノパーク(チュニジア)への言及)の協力、③投資、観光、金融、貿易分野の協力に焦点を当てたものとなった。また、前原大臣より明確に表明した日本の中東和平を支援する意思と、イスラエル入植活動に関する立場は、アラブ側より高く評価された。次回フォーラムは2012年に東京で開催される。
このほか、前原大臣とムーサ・アラブ連盟事務総長の会談では、日アラブ関係を政治・経済面に加えて文化面でも発展させることで一致、そのために有識者フォーラムを2011年中にも開催することとした。また、マグレブ諸国との間で、協力関係強化のための閣僚級懇談会が日マグレブ関係史上初めて行われ、インフラ整備や再生可能エネルギー等が共通の関心分野として確認され、今後、具体的プロジェクトにつながるよう協議を行っていくこととなった。
【第3回バリ民主主義フォーラム――日本からさらなる選挙関連支援を提案】
昨年12月9日、10日に、第3回バリ民主主義フォーラムが開催され、我が国より、前原外務大臣が出席しました。同フォーラムは、インドネシアのイニシアティブにより、民主主義の促進と発展のための政府間フォーラムとして2008年12月に設立され、以降、毎年、アジア各国の外相等の閣僚級の代表が多数参加しています。2009年は、我が国より鳩山総理(当時)が参加し、ユドヨノ・インドネシア大統領とともに共同議長を務めました。
前原大臣は、リーダーズ・セッションにおいて、「多様性の中の民主主義~アジアの特徴を力にして~」と題したスピーチを行いました。その中で、前原大臣は、アジアにおける民主主義の深化を促進するための基礎は、この地域が平和で安定し、力強く発展を続けて繁栄を実現することである旨述べ、そのための3つの鍵として、①力強い経済発展の継続、②地域協力の推進、③地域の安定の確保を指摘しました。
また、前原大臣は、アジアの多様性を尊重する必要性について触れ、多様な社会であるアジアの特徴は、全員が納得して参加できるように、着実な進展を辛抱強く積み重ねていく姿勢にあり、アジアの発展は、このような姿勢がまさに成果を上げていることを証明するものである旨指摘しました。そのほか、一昨年の本フォーラムで我が国が提案した「選挙訪問プログラム」について、昨年7月の我が国の参議院選挙の際に、アジア各国から選挙実務者を招待し、民主主義や我が国の選挙制度についてのセミナーを実施したこと、今年4月の東京都知事選挙の際に、再度「選挙訪問プログラム」を実施し、選挙実務者のためのセミナーを開催することを紹介しました。さらにバリ島において、各国が協力して「選挙訓練プログラム」を実施することを提案しました。
前原大臣のスピーチについては、各国から、前向きな、メッセージのある内容である等の高い評価が寄せられ、「選挙訓練プログラム」等の我が国の具体的な提案が議長声明に盛り込まれました。
【気候変動交渉――COP16に対する日本の評価】
2010年11月29日~12月11日にメキシコ・カンクンにおいて、気候変動枠組条約第16回締約国会議(COP16)が開催され、日本からは松本環境大臣ほか複数の政治家が参加した。COP16では成果文書として「カンクン合意」がまとめられた。カンクン合意では、コペンハーゲン合意に基づき、先進国と途上国の両方の排出削減プレッジが気候変動枠組条約の下で正式なものとして位置づけられるとともに、森林保全や資金、技術などに関する内容もバランスよく盛り込まれた。カンクン合意の採択に向けた議長国メキシコの努力に敬意を表するとともに、今回のカンクン合意を発展させた新しい一つの包括的な法的文書の採択に向け、日本は引き続き交渉の進展に尽力していく。
カンクンで議論の焦点になったことの一つは、京都議定書の第二約束期間の扱いについてである。現行の枠組みである京都議定書の第一約束期間が2012年末に終了するため、その後の国際枠組の在り方が現在議論されている。日本は、第二約束期間の設定には反対との立場である。真の地球益を考えれば、京都議定書で削減義務を課されていないが世界の排出量の40%を占めている米中を含む主要経済国が参加する、新たな法的な国際枠組みの構築が最善の道である。そのため、排出量の80%以上をカバーすると思われるカンクン合意を発展させ、あくまで公平かつ実効的な新たな国際枠組みを構築すべきと我が国は考える。(京都議定書は世界全体の排出量の27%しかカバーしていない。)
かかる立場は、日本のみの狭い利益やビジネス上の利害でとっているのではない。日本の意欲的な排出削減の取組はもちろん2013年以降も継続する。ここで第二約束期間のみを受け入れれば、2013年以降、京都議定書締約国のみが義務を負うという不公平かつ排出削減の観点から極めて効果的でない枠組みが固定化されることになり、かえってマイナスである。いったん第二約束期間を設定してしまうと、新たな法的枠組み構築への圧力が弱まり、現在のモメンタムを失ってしまう。短期的な「ディール」をして、今後10年間の問題をなおざりにすることはできない。そうしたディールは日本の国益のみならず、地球温暖化問題の解決そのものにとってもマイナスだからである。
【アフガニスタンに対する日本の支援パッケージ――日本は約16億ドルを実施】
我が国は、アフガニスタンに対して、2001年からこれまでに政治的支援、治安、インフラ整備、基礎生活分野、農業・農村開発、文化の分野での支援を実施してきたところ、改めて、2009年11月、治安、再統合、開発の3つの分野を柱として、今後のアフガニスタン情勢に応じて、2009年から概ね5年間で、最大約50億ドル程度までの規模の支援を行う旨を表明した。2010年末までに約10.4億ドルの支援を実施(2001年からの合計額は約25億ドル)。昨年11月には更に5.4億ドルの支援を決定し、各プロジェクトを実施する国際機関への拠出を行った。2009年から2010年末までの各分野における日本の支援実績は以下のとおり。
1.アフガニスタン自身の治安能力の向上のための支援 (約3.5億ドル)
アフガニスタン自身の手による国家再建を成し遂げるためには、同国における治安を確保することが重要。そのため、アフガニスタン自身の治安能力の向上を最大限支援すべく、我が国はUNDP/LOTFA(Law and Order Trust Fund for Afghanistan)を通じた警察官給与支援(全警察官給与の半分を支援。2009年:1.8億ドル、2010年:2.4億ドル)、警察強化研修等を実施し、アフガニスタン人自身が治安の責務を十分果たせるような道筋を作るための支援を実施した。その他、アフガニスタン国軍支援のため医療機材等を供与した。
2.元タリバーン等兵士の社会への再統合支援 (約1.5億ドル)
また、アフガニスタンの平和と安定のためには、軍事的取組のみならず政治的取組も重要である。この点、反政府勢力の社会への再統合と長期的な和解に向けて、当面元武装勢力の末端兵士及び下級司令官から再統合に取り組むことが重要であり、武器を置く者が再び反政府勢力とならず、自身の生活を営み、社会に復帰できるよう実効的な施策を構築していくことが不可欠となる。この施策の構築は、アフガニスタン政府が主導することが重要であるところ、我が国としては、旧国軍兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)、非合法武装集団の解体(DIAG)の経験と知見を活かしつつ、APRP(平和・再統合プログラム)の制度設計の段階から参画し、①アウトリーチ、②武装解除、③平和の定着という3段階の施策を進めるための財政的貢献を行っている。また、元兵士に対する職業訓練、雇用機会創出のための小規模開発プログラム等を併せ実施している。
3.アフガニスタンの持続的・自立的発展のための支援 (約5.3億ドル)
アフガニスタン国民を惹きつける国造りを進めることも重要である。我が国はこのような視点から、アフガニスタンの持続的・自立的発展のため、農業・農村開発、インフラ整備(エネルギー分野を含む)、教育、医療・保健等の基礎生活分野等の支援をニーズに合わせて実施してきた。また、アフガニスタンと国境を接する中央アジア地域を一つの面としてとらえて発展を促進することによってもアフガニスタンの安定を図ることが重要と日本は考えている。
【「医療滞在ビザ」の創設――健診・治療と観光を日本で一度に】
2010年6月に閣議決定された「新成長戦略」において、観光立国としての経済成長を図る我が国の国家戦略が掲げられた。具体的には、「今後、アジアからの訪日観光客を始めとした各国からの訪日外国人の増加に向けて、訪日観光査証の取得容易化、魅力ある観光地作り、留学環境の整備、広報活動等を図ることにより、訪日外国人を2020年初めまでに2,500万人、将来的には3,000万人まで伸ばす。」とされた。これを受け、2010年7月、中国人個人観光査証の取得容易化に係る措置が講じられた。その結果、2010年7月以降の各月において、同査証発給数が前年同月比で各約3倍~8倍に増加した。
また、日本政府は、2011年1月から「医療滞在ビザ」の運用を開始した。これは、健診、治療等の医療及び関連サービスを観光とも連携して促進していくことを目的に創設されたものである。同ビザは、必要に応じ、患者のみならず同伴者も利用できる(数次ビザが発給される)など、人道的観点も踏まえ、治療等で来日を希望する外国人にとって一層利用しやすいものとなるよう制度設計された。医療滞在ビザの創設により、より多くの外国人患者等が我が国を訪れ、我が国が誇る高度医療技術をもって健康になっていただくとともに、観光を通じて、日本文化など我が国の様々な魅力に触れていただきたいと願っている。(医療滞在ビザ制度の詳細については、外務省HPを参照:http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/medical_stay1.html)
【ジャパンエコー・ウェブ、Web Japan】
(日本の政策に関する国内論調や日本事情に興味がある方は、以下の「ジャパンエコー・ウェブ」及び「Web Japan」(英語説明文:Website providing information on Japan)HP(いずれも英文)をご覧ください。)
(ジャパンエコー・ウェブ) http://www.japanechoweb.jp/
(Web Japan) http://web-japan.org/
本レターに対するコメント等あれば、お知らせ頂ければ光栄です。
敬具
藤井 康司
在イラン日本国大使館 広報文化担当参事官