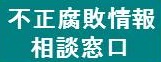 |
||
 |
||
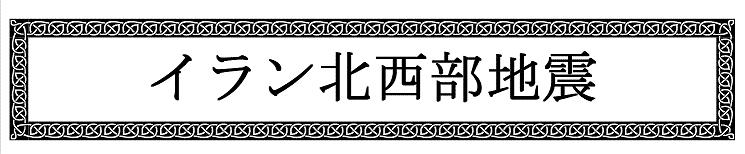 |
||
 |
||
 |
 |
 |
 |
 |
各種証明・申請手続きガイド |
2017年4月
領事班では、日本あるいはイランの関係機関に提出するために必要な各種証明書を発給しています。
証明書はその内容によっては個人の重要な身分事項にかかわるものや遺産相続のように財産にかかわるものなどがあり、発給に際しては証明書を必要としている方(以下、「当事者」といいます)の意思確認をはじめ、使用目的、提出先などを領事窓口で確認しております。また、交付時に証明手数料をお支払いいただく都合上、原則として申請時と交付時の二度の来館をお願いしております。
しかしながら、大使館の所在地から遠隔地にお住いの方や、高齢、病気や怪我、その他の事情により領事窓口への来訪が困難である場合は、代理人による代理申請や郵便による事前申請をお受けしておりますのでご利用ください。
ただし、署名証明は当事者の方に領事の面前で署名をしていただくことが必要であり、また警察証明は当事者の方の指紋を採取することが必要となりますので代理申請はできませんのでご注意ください。
証明手数料はすべての在外公館で同一料金(ただし現地通貨に換算します)ですが、標準処理日数(申請してから証明書を受け取るまでの日数)や申請書の体裁などは各在外公館で多少の差異がございますのでご了承ください。詳細につきましては申請先公館に直接お問い合わせください。
在イラン日本国大使館(領事班)
 |
目 次1.What’s New?!(領事班からのお知らせ)
|
 |
1.【領事部からのお知らせ】
| ◎証明手数料が改定されます。! |
2017年4月1日から証明手数料が改定されます。
手数料一覧は下記2.をご覧ください。
| ◎イランの自動車運転免許証の取得について |
日本の自動車運転免許証でイランの運転免許証を取得することができます。詳しくは、下記4.【各種証明手続きについて】の(5)【自動車運転免許証抜粋証明】の項をご覧ください。
| ◎旅券所持証明をご存じですか? |
イランでは、外国人に対するパスポートの常時携行義務に関する法律はないようです。しかし、路上で警察官等から職務質問され、パスポートの提示を求められることは十分考えられます。
パスポートを常時携行していれば問題はないのですが、万一、スリ、置き引き、車上荒らし、路上強盗等により紛失した場合、パスポートの新規発給にかかる諸手続や労働許可等の再申請等に相当の時間と経費を要してしまうことから、領事班としては、以下のことをおすすめします。
1.パスポートのコピー(人定事項と査証(滞在許可、労働許可等)のページ)を常時携行する。
2.Edareye Rahnamae va Ranandegi(日本の公安委員会に相当する機関)が発行する顔写真付き運転免許証を常時携行する。
3. 所属会社等から顔写真付き身分証明書を発行してもらい、常時携行する。
その他、領事班で発行する「旅券所持証明」(有料)を常時携行するのも一案です。但し、同証明の有効期限は、1年間(旅券の有効期限を超えない範囲)です。詳しくは領事班までお問い合わせください。
2.【手数料および標準処理日数一覧】 |
 |
種 類 |
標準処理 |
料金(Rials) |
在留証明 |
即時(原則) |
320,000 |
出生、婚姻、死亡等身分上の |
3日 |
320,000 |
翻訳証明 |
3日 |
1,190,000 |
署名又は印章の証明(官公署) |
3日 |
1,220,000 |
署名又は印章の証明(その他) |
即時~3日 |
460,000 |
その他の証明 |
3日 |
570,000 |
 |
申請書を以下の3種類から任意にお選びください。
②在留証明願 (注)①および②の両方の記入が必要となります。
③署名(および拇印)証明申請書 (注)①および③の両方の記入が必要となります。
 |
在外公館の領事窓口は、日本の市区町村役場における 「住基ネット」のようなシステムが整備されておりませ んので、申請を受理するにあたり、領事窓口では当事者の意思確認をはじめ、使用目的、提出先等を確認しております。これは発行される証明書の内容が個人の重要な身分事項にかかわるものや遺産相続手続きで使用するなど財産にかかわるものなどがあるためです。
従いまして当事者ご本人が領事窓口に出向いて申請・受理することが原則となりますが、やむを得ない事情により代理申請(受理)を行う場合は委任状が必要となります。
なお、申請を受理するときに領事窓口で確認させていただく公文書などの根拠資料はすべて原本の提示となります。
[委任状の書式]
所定の様式はありません。任意の委任状を作成してください。なお、委任状は提出となります。
委 任 状(例)平成29年○月○日
|
在留証明書は、日本国内における不動産登記手続きの際の住所確認、帰国子女の学校入学手続き、あるいは年金受給のための生存確認などさまざまな使用目的のために住民票の代わりとして使用されています。日本の官公署から提出を求められることが多いのですが、銀行などの一般企業からも求められることがあります。
在留証明書は、日本に帰国し、住民登録をした後は原則として申請することができませんのでご注意ください。また国民年金、厚生年金などの受給手続きにかかる空(から)期間を証明するために、社会保険事務所から外国に住んでいたことの事実を証明する書類を要求される場合がありますが、上記の通り、帰国後の申請はできませんので帰国後に在留証明書を必要とされる方は帰国前に必要部数を入手しておくことをお勧め致します。
◆証明内容
当事者が現在、イランのどこに住所(生活の本拠)を有しているか(現住所を証明します。形式1)、どこに住所を有していたか(現住所の証明と同時に過去の住所を証明します。形式2)、同居している家族(現住所の証明と同時に同居家族を証明します。形式2)を証明します。
◆発給条件
①日本国籍を有する者であること。
②当事者が現地にすでに3ヶ月以上滞在していること、または3ヶ月以上の滞在が見込まれていること。
③公文書などから外国の住所を立証できること。
④原則として、日本の住民登録を抹消していること。
⑤当事者が、原則として、申請先公館の管轄区域内に居住していること。
◆必要書類
①有効な日本国旅券(日本国籍の有無を確認します。旅券のかわりに戸籍謄(抄)本や券面上本籍が確認できる日本の運転免許証でも結構です。)
②現住所を立証できる公文書(または公文書に準ずるもの)を提示すること(納税証明書や公共料金請求書等で証明を必要とするご本人の氏名及び住所の記載があるもの。
③その他、現住所の証明と同時に滞在期間や過去の住所証明、同居家族の証明を行う場合は、それらを立証する書類が必要です。詳しくは領事部にお問い合わせ下さい。
◆所要日数 即時発行(20分~30分程度)
(注)恩給を含む公的年金受給手続きに在留証明を使用する場合は手数料が免除となります。手数料免除となる公的年金の種類は以下の9種類です。 《厚生労働大臣裁定》 ⑦援護年金 (注)社会保険庁長官が裁定する年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金等)の受給権者は、毎年誕生月に社会保険業務センターから生存確認のための現況届が送付されるため、誕生月の末日までに誕生月又は誕生月の前月に交付された在留証明書を添付し、社会保険業務センターへ提出することとなっています。 |
 |
出生証明書 |
◆証明内容
当事者がいつ、どこで出生したかを戸籍謄(抄)本などの公文書に記載された範囲内で証明します。外国関係機関あてに英語で発給します。
◆発給条件
①日本の市区町村役場が発行した公文書により出生事実を立証できること。
②申請は日本人の他、元日本人、日本で生まれた外国人も申請できます。
◆必要書類
①当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
②出生事実を立証する日本の市区町村役場が発行した公文書(戸籍謄(抄)本など。(注)外国人の場合は出生届受理証明書など)
◆所要日数 3日(受理日を起算日として3日目以降にお受け取りになれます。)
婚姻証明書 |
◆証明内容
当事者が誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明します。外国関係機関あてに英語で発給します。
◆発給条件
①日本の市区町村役場が発行した公文書により婚姻事実を立証できること。
②当事者は日本人に限ります。
◆必要書類
①当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
②婚姻事実を立証する日本の市区町村役場が発行した公文書(戸籍謄(抄)本、婚姻届受理証明書、婚姻届記載事項証明書など。
(注1)外国人(元日本人)の場合は婚姻届受理証明書など。戸籍謄(抄)本などの公文書は発行日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの。
(注2)外国人配偶者の場合は当事者(日本人)よりの委任状があれば申請が可能です。
◆所要日数 3日(受理日を起算日として3日目以降にお受け取りになれます。)
離婚証明書 |
◆証明内容
当事者がいつ正式に離婚したかを証明します。外国関係機関あてに英語で発給します。
◆発給条件
①日本の市区町村役場が発行した公文書により離婚事実を立証できること。
②当事者は日本人に限ります。
◆必要書類
①当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
②離婚事実を立証する日本の市区町村役場が発行した公文書(戸籍謄(抄)本、離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書など。
(注)外国人の場合は離婚届受理証明書など。戸籍謄(抄)本などの公文書は発行日より6ヶ月以内の可能な限り新しいもの。
◆所要日数 3日(受理日を起算日として3日目以降にお受け取りになれます。)
戸籍記載事項証明書 |
◆証明内容
戸籍謄(抄)本に記載されている「ある特定の身分上の事項」を証明します。
◆発給条件
①戸籍謄(抄)本を提示できること
②申請は日本人の他、元日本人も申請できます。
◆必要書類
①当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
②戸籍謄(抄)本(発行日より6ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
(注)父または母が外国人の場合は、父または母の旅券などで氏名綴りを確認します。
◆所要日数 3日(受理日を起算日として3日目以降にお受け取りになれます。)
婚姻用件具備証明書 |
◆証明内容
当事者が独身で、日本の法令上、婚姻可能な年齢に達していることを証明します。外国関係機関あてに英語で発給します。
◆発給条件
戸籍謄(抄)本により当事者が独身であり、日本の法令上、婚姻可能な年齢に達していることを立証できること。
◆必要書類
①当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
②戸籍謄(抄)本(発行日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
③離婚歴があり、それを明確に記載させる必要がある場合は、離婚の事実が記載された「除籍謄本」または「改製原戸籍」
◆所要日数 3日(受理日を起算日として3日目以降にお受け取りになれます。)
 |
◆証明内容
私文書上の署名(および拇印)が当事者の署名(および拇印)であることを証明します。署名は領事の面前で行います。証明書と当事者ご本人が面前署名した文書とを綴り合わせて割り印をするもの(形式1)と単独の署名証明(形式2)があります。
◆発給条件
①当事者は日本人に限ります。
②当事者ご本人が領事窓口に出向き、領事の面前で署名すること。
③当事者は原則日本の住民登録を抹消していること。
◆必要書類
①当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
②署名すべき文書(形式1の場合)
◆所要日数
①形式1の場合 午前中の申請は午後に交付。午後の申請は翌日以降の交付。
②形式2の場合 即時発行(20分~30分程度)
 |
◆証明内容
当事者が作成した翻訳文が原文書(日本の公文書)の忠実な翻訳であることを証明します。外国関係機関あてに英語で発給します。
(注1)翻訳証明は、原文書の内容の真実性までを証明するものではありません。
(注2)日本の法令規則、訴訟に関する裁判所の文書は例外として翻訳証明の対象となりません。また外務本省(東京)や在外公館が発行した文書についても原則として翻訳証明の対象となりません。
◆発給条件
①対象となる原文書は、原則として日本の市区町村役場が発行した公文書であること。私文書は対象となりません。
②私文書であっても日本の公証人の公証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明がある文書は対象となります。
(注1)有効期限のある公文書(例えば運転免許証など)は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは原則として発行後6ヶ月以内のものに限りますが、可能な限り新しいものをご提出ください。なお、学位記など再発行されないものについては発行年月日に関わりなく申請することができます。
(注2)学校教育法第1条に基づき設立された私立学校の発行した卒業証書や成績証明書は公文書に準ずる文書として申請することができます。
③原文書の原本を提出できること。
④翻訳文を当事者が持参すること。
◆必要書類
翻訳証明の対象となる原文書および翻訳文
(注)必ず翻訳文を持参してください。
◆所要日数 3日(受理日を起算日として3日目以降にお受け取りになれます。ただし、原文が長文の場合、あるいは専門用語が多用されている場合には、さらに日数を要することがありますのでご了承ください)
 |
◆証明内容
当事者がわが国の自動者運転免許を有していることを証明します。関係当局へは、当証明の公証ペルシャ語訳を提出することになります。
◆発給条件
現に有効な日本の自動車運転免許証を有していること。
◆必要書類
有効な日本の自動車運転免許証
◆所要日数 3日(受理日を起算日として3日目以降にお受け取りになれます。)
*日本の運転免許証からイランの運転免許証を取得する手続きについては こちらをご覧ください。
 |
米国、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア等へ の永住申請手続きを行う、あるいはヨーロッパで商業活動 を行うために長期滞在(就労)査証を申請するなど、様々なケースで外国関係機関よりその国の法律に基づき、警察 証明書の提出を要求される場合があります。
警察証明書は在外公館限りで発給することができない証明書であるため、在外公館は当事者からの申請を受け付け、警察庁に対して発給取次依頼を行っています。
海外に居住している方が一時帰国の際に申請を行う場合は、最終住所登録(外国人登録)をしていた市区町村を管轄する警察本部(警視庁、各都道府県警察本部)が窓口となります。窓口受付時間・必要書類・発行までの日数・手数料等の詳細については、直接警察本部にお問い合わせください。
(注)警察署での申請はできません。
警察証明書(問い合わせ先) ◎警察庁/National Police Agency 〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2 (中央合同庁舎2号館) ◎警視庁/Metropolitan Police Department |
◆証明内容
当事者の日本国内における犯罪歴の有無を日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語の5カ国語で証明します。在外公館受け付け分はすべて警察庁が発行します。
◆発給条件
①当事者は日本人に限らず、外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。
②現地関係当局がその国の法規に基づき、当事者に対して警察証明書の提出を要求している事実が確認できること。
③領事窓口での申請時に、当事者ご本人の指紋採取を専用紙(指紋原紙)に採取しますので代理申請は認められません。
(注)領事窓口で指紋採取を行う場合、申請書の記入から指紋採取の一連の事務手続きが終了するまでに20分から 30分ほどかかります。お住いの地域を管轄している現地警察署などであらかじめ指紋採取したものを持参することもできますが、指紋原紙を事前に入手しておくことが必要です。
◆必要書類
①当事者を確認できる公文書(公的機関が発行した写真付き身分証明書;旅券など)
②指紋原紙(申請時に領事窓口でお渡しします。)
◆郵便申請
事前に当事者ご本人の指紋を採取するための専用紙(指紋原紙)を入手する必要がありますので、返信用の切手を貼付した封筒(A4サイズ、宛先、受取人記入済のもの)を同封の上、指紋原紙の送付依頼を行ってください。後日、指紋原紙の他、申請書、必要書類の案内などを送付致します。
◆所要日数 約2~3ヶ月
(注)在外公館申請分は外務本省(東京)を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上、お手元に証明書が届くまでに概ね2~3ヶ月、場合によっては3ヶ月以上かかることもありますので、ご了承下さい。
◆手数料 無料